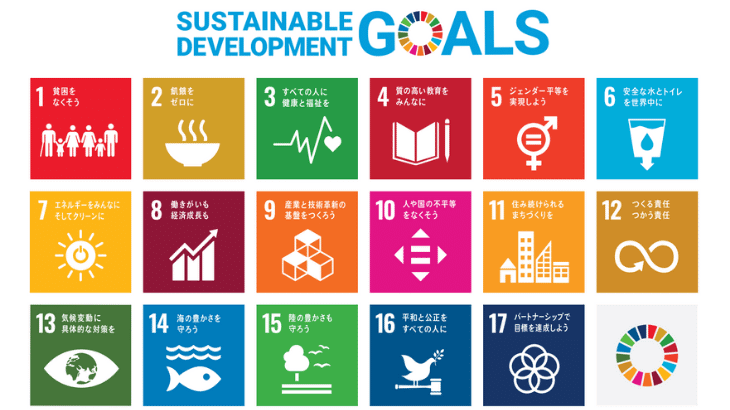海岸線をドライブした際、海面が赤く濁っているような光景をみたことがある方も多いのではないでしょうか?本コラムでは、海面が赤く見える減少である「赤潮」に発生のメカニズムや生態系への影響まとめました。
「赤潮」とはどんな現象?

赤潮とは、人々の活動などによって、海の栄養分が増えることで、植物プランクトンが過剰に発生し、海面が赤く見える現象のことです。赤潮は、海水中に生息する藻類が増殖し過ぎることが原因で発生します。このとき、藻類が多量に排出する色素が海水を赤く染めるため、赤潮と呼ばれます。
ニュースになるくらい、大規模な赤潮が生じることもあります。
トイレやお風呂などの生活排水や、工場での排水等によって栄養分が増加し発生することが多く、日本では「東京湾」はもちろん、狭い地形である「瀬戸内海」などでもよくみられる現象です。
「栄養塩」と「富栄養化」というキーワード!
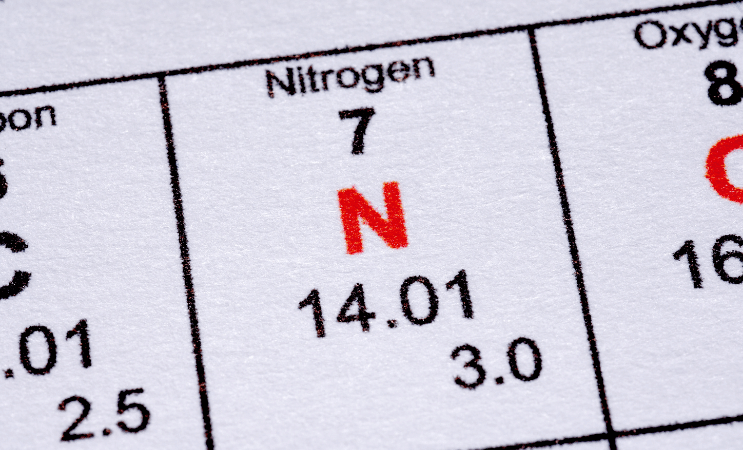
さて、栄養というと人間の場合「ミネラル・タンパク質・脂質・ビタミン」と言ったものを思い浮かべるでしょうか?科学や生物学の分野においては、窒素・リン・ケイ素などの微量な元素のことを指します。
そして、これらのことを
植物プランクトンにおいての3大栄養素は「窒素・リン・ケイ素」です。以下、栄養塩という言葉があったらこれらをイメージしながら読み進めてください。また、植物プランクトンの栄養源となる「栄養塩」が過剰になった状態のことを
反対に、「貧栄養化」という言葉もあり、栄養塩が著しく少ない状態を指します。透明度の高い湖などが、これに当たることが多いです。合わせて、このキーワードも抑えてもらうといいでしょう。
「赤潮」のなにが問題なのか?

赤潮が発生すると大きく3つ、問題となることがあります。
①魚が死んでしまう
富栄養化の結果、植物プランクトンが過剰に発生すると、やがて大量の植物プランクトンの死骸が漂うことになります。すると、その海域に住む魚のエラに、植物プランクトンの死骸がつまり、酸欠状態になった魚は、死んでしまいます。
また、藻類が多量に排出する酸性物質や過酸化水素は、海洋生物の体内に取り込まれると、内臓を傷めることもあります。
また、その海域に存在するバクテリアは植物プランクトンや魚の死骸を分解しようとするため、大量の酸素が消費されます。その結果、魚が酸欠して死んでしまうこともあります。
②養殖産業に大ダメージの可能性
日本では養殖産業が盛んです。スーパーに行けばブリやハマチなど、リーズナブルで美味しい魚が並んでいますね。さて、養殖がどのような場所で行われているかご存知でしょうか?

上記の画像のように、養殖は沿岸部、湾の中で行われることが多いです。なぜならば台風などの自然現象の影響を受けにくいため、施設を管理するのに歴しているからです。
では、こう言った湾内で赤潮が発生するとどう言ったことが起こるでしょうか?
まず、湾内で赤潮が発生すると、海域が酸欠状態になります。また、養殖魚のエラには植物プランクトンの死骸がつまり、酸素を十分に供給できなくなります。結果、大量の養殖業が死んでしまうということになります。
また、漁業従事者は、大きな損害を受けてしまいます。その結果、魚類の値上げをしなければならない、なんてことも起こりうるのです。
 漁業の種類を解説!沖合・遠洋・沿岸・養殖漁業とは?
漁業の種類を解説!沖合・遠洋・沿岸・養殖漁業とは?③景観などの問題
3つ目は景観的ダメージや、臭いと言った部分です。例えば人気のドライブコースとなっている沿岸付近で赤潮が生じれば、綺麗な海を見ることはできません。また、沿岸部に住む人々は、赤潮が生じた場合、生臭い匂いに悩まされなければいけません。
さらに、赤潮が発生しやすいイメージが人々に定着すると、観光地として人気がなくなり、地域経済にも悪影響を与えます。赤潮は、沿岸部や海岸沿いの地域にとって、大きな問題となる現象です。そのため、赤潮の発生を防ぐための取り組みが必要です。
 陸上養殖とは?種類・メリットとデメリットをわかりやすく解説
陸上養殖とは?種類・メリットとデメリットをわかりやすく解説「赤潮」の発生を予防・抑制する方法
赤潮の発生は海洋生態系に大きな影響を与えます。しかし、予防と抑制の方法を理解すれば、その影響を最小限に抑えることができます。
排水を見直す
まず、赤潮の発生には様々な要因が関係しますが、その中でも水質汚染が大きな要因となります。具体的には、排水や農薬などに含まれる窒素・リンなどの栄養塩が海に流れ込むと、これらが赤潮を引き起こすプランクトンの増殖を助けてしまいます。
そこで、農薬の適正な使用や生活排水の処理を徹底することが重要です。
赤潮を早期発見できる体制を整備する
また、赤潮の早期発見と迅速な対応も大切です。赤潮の発生を早期に察知し、海水の循環を促すなどの対策を行うことで、赤潮の拡大を防ぐことができます。最後に、これらの対策は個々の行動だけでなく、地域や国家レベルでの取り組みも必要です。
赤潮と密接な関係にある「アオコ」
赤潮と密接な関係を持つ自然現象の1つに、「アオコ」という現象が挙げられます。赤潮を理解する上でも重要な要素なるので、以下に紹介いたします。
「アオコ」とは?
アオコは、一般的には赤潮の一種とされ、実際には青色から緑色を呈する現象です。アオコが発生すると、水中の酸素が減少し、魚や甲殻類などの水生生物に悪影響を及ぼすことがあります。
また、アオコは、特定の藻類が大量繁殖することで発生します。この藻類は、水質汚染や栄養塩の過剰な供給が原因で急激に増えます。
アオコが発生すると、水中の酸素が減少し、魚や甲殻類などの水生生物に悪影響を及ぼすことがあります。また、アオコの藻類は有毒種も含まれ、人間が摂取すると健康被害を引き起こす可能性もあります。(このような影響を防ぐためには、水質管理が重要となります。)
「アオコ」が「赤潮」を引き起こす過程
赤潮は海水中の養分が増え、特定のプランクトンが大量繁殖することで海が赤く染まる現象です。一方でアオコは、赤潮が収束した後に頻繁に見られる現象で、別種のプランクトンが優勢になり、海水が緑色に見えるようになります。赤潮が発生した後、養分が枯渇し、赤潮を引き起こすプランクトンが死滅します。その結果、生存競争に勝つことができた別のプランクトン種が大量に増え、アオコ現象が起こります。
アオコは普段は海洋生態系の重要な一部で、光合成により酸素を供給し、食物連鎖の基盤を形成します。しかし、養分が過剰に供給されると、アオコは急速に増殖し、海を真っ赤に染め上げる「赤潮」を引き起こします。これが「アオコ」が「赤潮」を引き起こす過程です。
また、アオコが生成する毒素は、貝類や魚類に蓄積し、人間が摂取すると食中毒を引き起こすこともあります。なお赤潮は自然現象ですが、人間の活動が原因で増加しているとも考えられています。
 生物濃縮とは?仕組みや影響についてわかりやすく解説
生物濃縮とは?仕組みや影響についてわかりやすく解説まとめ

赤潮という現象は
- 酸欠状態になり魚が死んでしまう
- 養殖漁業にダメージの可能性
- 景観面や臭いと言った部分で悪影響
という影響を及ぼします。
そして赤潮の原因となる「富栄養化」の元を辿ると、生活排水や工業廃水と言った人間活動によるものということを、お分かりいただけたと思います。
企業や政府だけでなく、個人としてもこの流れを理解した、環境に優しい行動ができるといいのかもしれませんね。
 漁業組合とは?組織の仕組みや漁師との関係を説明します!
漁業組合とは?組織の仕組みや漁師との関係を説明します!