SDGsは、世界的に広がり多くの人々や企業、行政などが取り組んでいます。東日本大震災で甚大な被害にあった東北地方(東北6県)においても、SDGsへの活動は盛んになっているのが現状です。東北地方の行政やNPO団体、市民、大学などが、さまざま形でSDGsの目標達成に取り組んでいます。
その東北地方は、米どころでもあるため、SDGsをお米作りに反映しているケースも少なくありません。本記事では、東北のSDGsの取り組みや内閣府における東北地方創生のSDGsへの取り組みを解説します。東北のお米作りの歴史を紐解きながら、お米を通したSDGsの取り組みも紹介するので、ぜひ参考にしてください。
東北地方6県(青森・秋田・岩手・山形・宮城・福島)の復興とSDGs(復興庁)

「誰一人取り残さない(Leave no one behind)」はSDGsの前文に掲げられている中核的理念です。東北地方でも、東日本大震災からの復興に向かっている最中で、被災地の多くの人が心に思ったことでもあるのではないでしょうか。
一般社団法人SDGs市民社会ネットワーク事務局長は、「今のままのやり方ではもたない。トランスフォーム(変革)しなければならない」としています。さらに、「SDGsへの認識は、被災地が感じている危機感と重なる」とも指摘しているのです。SDGsを捉え直すことによって、復興とSDGsについて、新たな課題が発見できるのではないでしょうか。
東北地方の代表的なSDGsへの取り組み
東北地方では、震災からの復興とともにSDGsにも取り組んでいます。ここでは、代表的な取り組みを3つ紹介します。
「一般社団法人SDGsとうほく」の取り組み
2030年までに、SDGsの17の目標を達成するために、企業やNPO、NGO、自治体、市民などが連携し、地球と共生する循環型社会をつくることが目的です。東北地方ならではの課題に向き合って、東北地方ならではの魅力を広げる取り組みを展開しています。東北地方の1人ひとりが、幸せに暮らせる新しい文明の魁となる取り組みです。
とうほくSDGsアワードを開催
2024年には、「とうほくSDGsアワード」が開催されました。東北地方ならではの、独創的なサステナブル(持続可能)な活動にスポットを当てる賞です。自然豊かな東北地方であっても、自然環境の保全やレジリエントな街作りは不可欠となっています。
また、福祉や教育の充実といった社会的ニーズへの対応も喫緊の課題です。そこで、「一般社団法人SDGsとうほく」と「東北大学大学院経済学研究科」が主催し、「東北経済産業局」や「河北新報社」、「株式会社オルタナ」の後援を得て本アワードを開催する運びとなりました。
東北6県のなかで、企業や団体などの優れたSDGsへの取り組みを顕彰することは、企業や市民、行政の各セクター間での学びが深まります。SDGsの深化により、地域課題の解決が促進されることも大きな目的です。
東北工業大学の持続可能な未来の東北をつくる TOHTECH with SDGs

東北工業大学では、SDGsの理念や行動が社会に定着する傾向を踏まえ、SDGsへの寄与や深化を目指しています。この取り組みを教育や研究、社会貢献、大学運営全般に広めて一層深めているのです。
この姿勢を <TOHTECH with SDGs>として社会に向け改めて宣言し、東北地方の社会や市民とともに推進できるように努めています。東北工業大学の研究内容の一例は、次のようになります。
- ヒトiPS細胞とエレクトロニクス・AI技術の融合により創薬に貢献
- 会計情報の活用とSDGs経営を実践する中小企業の調査研究
- 地域らしさを深めるデザイン研究
- 歴史ある建物を未来へ伝える保存修復と活用
- においを可視化により呼気による健康管理を可能にする社会
- 個へのアプローチから壁のない社会をつくる
これらの取り組みは、すべてSDGsに貢献し深化につながるものです。また、上記以外にも、多種多様な研究が進められています。
内閣府地方創生の東北地方におけるSDGs
内閣府の地方創生では、SDGsへの取り組みが積極的に行われており、東北地方でも多くの県や地方、地域などでSDGsに取り組んでいます。そのなかでも、自治体SDGsモデルとなった代表的な取り組みを2例紹介します。
青森県弘前市のSDGs未来都市の取り組み

青森県弘前市では「SDGsで未来につなぐ日本一のりんご産地実現プロジェクト」を推進しています。青森県弘前市は、日本一のりんごの産地ですが、担い手が減り遊休農地が増加していることが課題です。この課題を解消することはSDGsに貢献します。
そのために、持続可能な「日本一のりんご産地」を目指すことを真剣に取り組んでいるのです。具体的には、革新的なりんご生産に取り組んで、農業所得を向上させています。また、無煙炭化器の導入やバイオマス発電など、環境負荷への軽減も成功しました。これらにより、二酸化炭素排出量を削減し、循環型農業を推進しています。
参考:SDGsで未来につなぐ日本一のりんご産地実現プロジェクト
宮城県石巻市のSDGs未来都市の取り組み

宮城県石巻市では、「コミュニティを核とした持続可能な地域社会の構築」に取り組みSDGsに貢献しています。グリーンスローモビリティによる新たな移動手段の構築がこの取り組みの柱です。ハイブリッドリユース事業で生産された電気自動車をカーシェアリングで活用しています。
グリーンスローモビリティとは、時速20km未満で公道を走ることができる電動車を活用した小さな移動サービスです。また、この電気自動車は、100%自然エネルギーで走行します。ハイブリッドリユース事業により、産業として雇用も創出しました。
高齢者のデジタルデバイド(情報格差やデジタル格差)を解消するため、コミュニケーションロボットで容易にMaas(マース)に接続し、配車できるようになっています。MaaSとは、Mobility as a Serviceの略語であり、利用者のニーズに合わせて複数の移動サービスを組み合わせて検索・予約・決済などを行うサービスです。
東北地方とお米
東北地方は、日本最大のお米の生産地として有名です。生産量の現状やどのような歴史があるのかを知ることで、SDGsとの関連が分かりやすくなります。
東北地方のお米の生産について

東北地方の米作や農業と聞けば、宮沢賢治を思い浮かべる人も少なくないのではないでしょうか。宮沢賢治は、東北地方の米作や農業に深い関心を持ち、その作品にも米や稲などの穀物が数多く登場しています。
現在では、東北地方が全国の中でも最も多くのお米の生産地となっています。令和4年度の全国お米生産に占める東北のお米の生産割合生産量は、194万8,000tで生産割合は27%です。また、東北地方で開発されたお米であるひとめぼれやあきたこまちなどの品種は、全国的な知名度があります。東北各県の農業生産額では、青森県以外では各県がお米の生産が1位です。
東北地方のお米生産の歴史

現在では、日本の米どころとなっている東北地方ですが、お米の生産が盛んになるまでには長い歴史があり、概略は次のようになります
- 弥生時代前期から中期にかけて稲作が行われていたと考えられる
- 寒冷な気候や自然災害の影響で弥生時代後期には稲作を停止
- 712年に出羽の国(山形県と秋田県に相当した旧国名)が置かれてから本格的に開墾
- 江戸時代では、度重なる冷害や凶作があった
- 庄内藩主酒井忠勝が稲作を奨励したことにより増産
- 明治時代には、生産技術の向上を目指した多くの活動を展開
- 昭和6年~10年にかけての冷害で深刻なダメージを受けた
- ササニシキが奨励品種に採用され、収穫量が大幅に増えた
昭和の時代以降はさらに品種改良が進み、日本を代表するような品種が次々に排出されています。
東北のお米とSDGsの取り組み
東北地方では、お米が主力の農産物であるためSDGsに関してもさまざまな取り組みがあります。お米が主力となった経緯には、先に述べた歴史に加えて、工業地帯などが少なく平野を確保しやすかったことが大きな理由です。
豊かな山々と川が作る肥沃な大地により、日本のお米の約1/4が6県で作られています。品種も多種多様となっていますが、SDGsに関連する取り組みを行っているケースも少なくありません。ここでは、その代表的な例を3つ紹介します。
安心・安全みやぎの環境保全米
みやぎ(宮城県)の環境保全米とは、豊かな水と土を美しく保ちながら、自然豊かな環境を守ることに留意したお米です。農薬や化学肥料の使用量を半分以下に減らしたお米作りを進めています。これは、自然と人間の力をあわせておいしいお米作りを行うことが目的です。
みやぎの環境保全米の生産により、水や土を守れるため、生物の生態系の保全にもつながります。そのうえ、安心で安全なお米をユーザーに届けられるのが大きなメリットです。この取り組みは、安定した食糧供給にも貢献しています。
福島県浪江町の田植えイベント

総合家庭用品メーカーが主導している取り組みもSDGsの貢献に有効です。東日本大震災の被災地であり、原発事故の被災地でもある福島県浪江町で、2021年に東北農業の課題解決と営農再開に向けて活動を開始しました。同メーカーは、この支援活動を「東北農業の未来をつなぐ、創るプロジェクト」と称しています。
福島県沿岸部は、農地のインフラ整備が遅れているだけではなく、担い手の不足や風評被害などにも直面しました。これにより、お米の販路縮小など多くの課題が山積しているのが現状です。同メーカーは、玄米の買取りを継続するなどの被災地域の課題解決に貢献しつづけています。これは、SDGsだけではなく、原発事故の復興にも寄与しているといえるでしょう。
青森の「米づくり新時代」推進方策
青森県は、りんごの栽培が盛んであり、東北6件のなかで唯一お米が生産1位ではない県です。しかし、SDGsの取り組みも合わせて、お米作りにも注力しています。2015年にデビューした「青天の霹靂」は、その後8年連続で米の食味ランキングで「特A」評価を取得しました。
SDGsに貢献するために、次のようなお米作りの取り組みに注力しています。
- 高値で売れるプレミアム米の生産拡大
- 省力や低コスト、多収にわたる生産費の削減
- 将来を見据えた輸出拡大へのチャレンジ稲作の技術革新を支える研究開発の推進
これらの取り組みは、持続可能なお米生産を目指しており、SDGsへの取り組みにも貢献しています。
まとめ

東北地方は、甚大な被害を受けた東日本大震災の復興の最中にありながら、SDGsへの取り組みも進めています。代表的なのは、一般社団法人SDGsとうほくの取り組みやとうほくSDGsアワードなどです。これらに加えて、内閣府地方創生においても、SDGsの取り組みを後押ししています。
なかでも、優れた取り組みに対しては、「自治体SDGsモデル」として発表しました。これは、他の自治体の模範となることが狙いです。また、東北地方は日本の米どころとして有名であり、生産量も国内のお米の1/4以上を生産しています。
東北地方のお米作りにおいても、SDGsに取り組んでいるケースが少なくありません。宮城県の環境保全米や福島県浪江町の田植えイベントなどが、代表的です。また、米農家独自や企業、行政が主体となった取り組みも数多くあります。今後も、東北地方では、SDGsを取り入れたお米作りが増えていくでしょう。
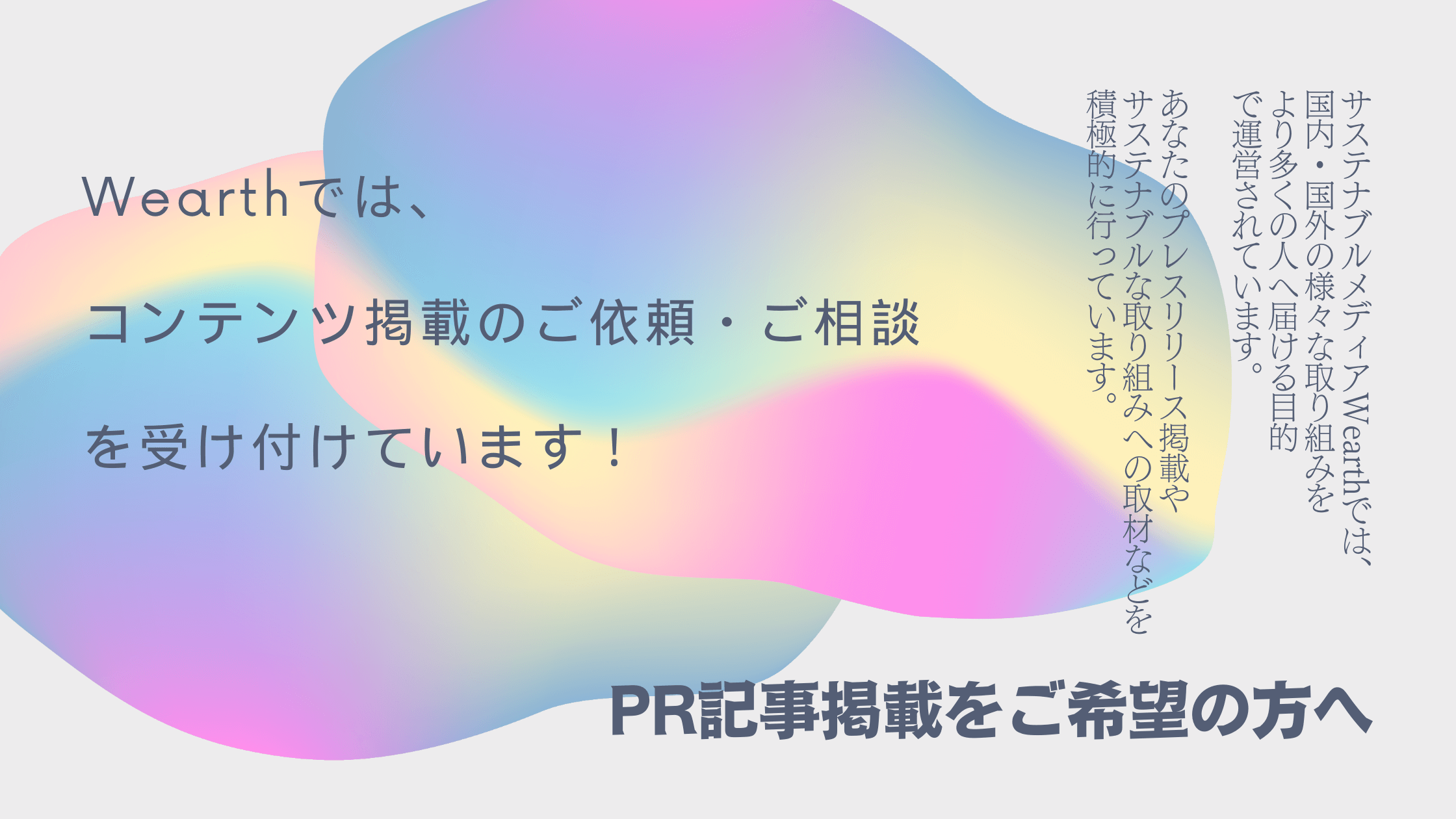
サステナブルメディアWearthでは、国内・国外の様々な取り組みをより多くの人へ届ける目的で運営されています。
あなたのプレスリリース掲載やサステナブルな取り組みへの取材などを積極的に行っています。
※法人/個人を問いません、まずはご相談ください
※事前に掲載したい記事草案をご用意いやだけますとスムーズです



