「エシカルな〇〇」など、“エシカル”という言葉がよく使われるようになりました。では、エシカル消費と言われるものは、どういった消費のことをさすのでしょうか?
本記事では、エシカル消費とSDGsとの関係性やエシカル消費の具体例を紹介します。
エシカルとは?

エシカルとは、英語でethical、「倫理的な」という意味です。この言葉から派生して、エシカルは「人や環境に配慮した」という意味で使われるようになりました。本記事では、エシカルな“消費”に着目したいと思います!
まず、「エシカル消費」について、消費者庁は次のように定義しています。
消費者それぞれが各自にとっての社会的課題の解決を考慮したり、そうした課題に取り組む事業者を応援しながら消費活動を行うこと。
エシカル消費とは | 消費者庁
つまり、「エシカル消費」とは、人や社会、自然環境などを配慮した商品やサービスを購入することを言います。
日本で最初のエシカル団体(2010年設立)であるエシカル協会の代表末吉さんはエシカル消費を「過去・現在・未来を考えて消費すること」と表現しています。
エシカルがなぜ注目されるのか?

近年のトレンドとも言える「エシカル」の動きですが、なぜ、エシカル消費がこれほど注目されるのでしょうか?次は、その役割について確認しましょう。
GDPにおいて消費が占める割合
消費の中でも個人消費は社会や経済を動かす大きな影響力をもっています。
日本のGDP(国内総生産)のうち、個人消費は約5割を占めています(令和元年度版消費者白書)。
つまり、大きく言えば、毎日の買い物をエシカルにすることで世界を変えることができるのです。
SDGsとの関係性
エシカル消費は、SDGs目標のほぼすべてのターゲットにかかわるアクションです。
とくに目標12.「つくる責任えらぶ責任」には、「持続可能な生産・消費形態の確保」が掲げられており、まさにエシカル消費がこの役割を担っていることが分かります。
加えて、消費者庁消費者政策課によると、日本の食品ロス量は年間646万トン(平成27年度推計)というデータが公開されています。
つまり、人や社会、自然環境などを配慮した製品を積極的に活用することで、食品ロスなどの社会問題に取り組んでいくことができるという考え方であるのです!
ポストコロナ時代へ
エシカルな商品、販売は企業や労働者をパンデミックといった不測の事態から守ってくれる力があることが今回の新型コロナ感染拡大で証明されています。
新型コロナ感染拡大で世界ではロックダウン、日本では緊急事態宣言など、都市部を中心に人や流通の動きがとまる事態が起きました。
こういった世界経済の大きな変動に対し、エシカルに力を入れてきた企業(NIKEやH&Mなど)は生産、流通をとめず、大きな混乱を作らないような対応をとったと言います。
持続可能性を考慮した経営の在り方がパンデミックの時に企業のリスクマネージメントとして機能したことが言えます。

エシカル消費の具体例

エシカル消費が注目されている背景を押さえたところで、次は具体例を見ていきましょう。
エシカル消費は消費生活全般にかかわるので様々なかたちがあります。ここではすべてを取り上げることができませんが、代表的なものをいくつか紹介しましょう。
フェアトレード
エシカル消費で最も有名な取り組みと言えるのがフェアトレードです。フェアトレードは発展途上国など経済的に弱い立場の生産者が購入する側(主に先進国)と公平で適正な価格の取引をすることを言います。
フェアトレードの国際認証を受けたコーヒー、紅茶の他にも、企業や個人が独自に基準を設定して直接取引をした衣類や食品もあります。
エシカルファッション
エシカルファッションはオーガニックコットンやアップサイクルの衣類、毛皮などの不使用、フェアトレードの衣類や化粧品などをいいます。
これと似た概念でサステイナブルファッションがあります。サステイナブルファッションについては、関連記事をご覧ください!
 サステナブルファッションとは ?取り組みの背景やブランド5選を紹介
サステナブルファッションとは ?取り組みの背景やブランド5選を紹介地産地消
地域でとれた農林水産物や製品を購入する地産地消もエシカル消費です。
地産地消のエシカルな点1つ目は、生産者と消費者が近いことです。両者に信頼と愛着が生まれ、経済を支え合う相互扶助を生みます。
2つ目のエシカルな点は、物が消費者に渡るまでの距離が短いことです。
輸送で排出されるCO2の削減になります。その他にも、被災地の復興支援の応援消費、伝統工芸を守ることもエシカル消費です。
再生可能エネルギー
太陽光発電、風力発電、水力発電など再生可能エネルギーを選択していくのもエシカル消費です。
電気自動車などのエコカーを選択していくこともそうでしょう。電気会社によっては売り上げの一部をこども食堂の寄附に回すといった試みもあり、こういった電力会社を積極的に選択していくこともエシカルと言えます。
 SDGs目標7「エネルギーをみんなにそしてクリーンに」を解説!
SDGs目標7「エネルギーをみんなにそしてクリーンに」を解説!認証ラベルのついた商品
エシカル消費はこのように様々な分野にわたるので、何がエシカル消費なのか、迷子になってしまう人もいるかもしれません。そういった時に助けになるのが認証ラベルです。買い物の際には、ぜひ参考にしてください。
注目したい認証ラベルは以下の表の通りです!
| 認証/ラベル名 | 対象となる商品 |
| エコマーク | 環境保全に役立つ商品 |
| 国際フェアトレード認証 | 国際フェアトレード基準が守られている商品 |
| 有機JASマーク | 自然界の力で生産された食品 |
| MSC | 水産資源と環境に配慮された製品 |
| ASC | MSCの養殖を対象としたもの |
| RSPO認証 | パーム油の生産基準が持続可能なものであることが聡明された製品 |
| レインフォレスト・アライアンス認証 | 持続可能性の3つの柱(社会・経済・環境)の強化につながる手法を用いて生産された製品 |
| ふるさと(地域特産品)認証食品 | 優れた品質、正確な表示、地域への環境と調和した食品 |
| OCS | オーガニック繊維製品であることを証明される製品 |
| RDS(Responsible Down Standard) | ダウンとフェザーが不必要な危害を受けていない動物由来であることを証明する製品 |
エコマーク
環境への負荷が少なく、環境保全に役立つと認められた商品に付けられる環境ラベルです。
実さに目にしたことがあるかたも多いのではないでしょうか。
国際フェアトレード認証
国際フェアトレード認証は、国際フェアトレードラベル機構(Fairtrade International)が定めた国際フェアトレード基準が守られていることを証明するラベルです。
有機JASマーク
有機JASマークは、農薬や化学肥料などの化学物質に頼らないことを基本として自然界の力で生産された食品に付けられるマークです。
▼参考記事▼
【有機食品・コスメ・繊維】オーガニック認証とは?
MSC「海のエコラベル」
水産資源と環境に配慮し適切な管理を行っているとして認証された漁業で獲られた水産品に付けられるラベルです!
MSCの養殖版ラベルとして、ASC認証というものもあります。
▼参考記事▼
「サステナブルシーフードってなに?言葉の定義と具体例を紹介します!」
RSPO認証
RSPO認証は、パーム油の生産基準が持続可能なものであることを保証するラベルです。
レインフォレスト・アライアンス認証
レインフォレスト・アライアンス認証は、製品または原料(農産物、林産物、観光業)が、持続可能性の3つの柱(社会・経済・環境)の強化につながる手法を用いて生産されたものを示すラベルです。
ふるさと(地域特産品)認証食品
ふるさと(地域特産品)認証食品は、農林水産省が提唱したマークです。優れた品質、正確な表示、地域への環境と調和した食品を示すラベルと言えます。
認証マークは各都道府県によって若干異なりますが、マークは、
・優れた品質(Excellent quality)
・正確な表示(Exact expression)
・地域の環境と調和(Harmony with Ecology)
の3つのEを「品」の形に配置し、「良い品(イイシナ)」であることを表しています。
OCS
原料から最終製品までの履歴を追跡し、その商品がオーガニック繊維製品であることを証明するラベルが、OCSオーガニック認証です。
有機製造方法に関する規則等に従った有機農法の認証を受けている原料を使用しており、また製造過程が明確に追跡できることが求められます。
RDS(Responsible Down Standard)

Responsible Down Standardとは、ダウンとフェザーが不必要な危害を受けていない動物由来であることを保証するラベルです。
ユニクロ公式サイトからも確認できます。
エシカル消費に重要な5つの配慮
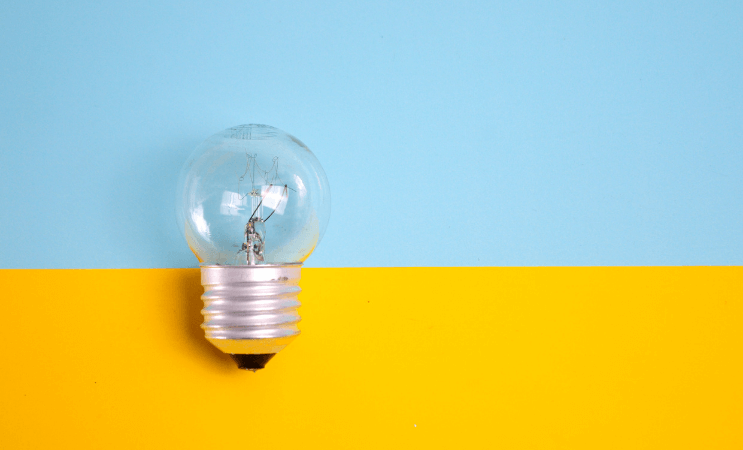
エシカル消費のポイントとして次の5つに配慮されていることが重要です。
(参照:消費者庁ガイドライン)
- 人への配慮
- 社会への配慮
- 地域への配慮
- 環境への配慮
- 生物多様性への配慮
これらは互いに別々のものではなく、相互関係を持っています。例えば、環境に配慮したエシカル商品を購入することで、環境が守られ、生物多様性が守られます。
また地産地消をすることで、地域経済が潤い、収入を得られるので地域、人への配慮になります。フェアトレード商品を購入することで社会や環境への配慮にもなります。
いろいろな角度からエシカル消費をすることで、よりサステイナブルな社会に近づいていくのです。
【エシカル消費】課題と解決例

エシカル消費は次のような社会的問題を解決する方法として有効です。ここでは3つ、具体例をご紹介してきます!
①児童労働
劣悪な環境下で子供たちが労働を強いられていることがあります.
例えば、化粧品の原料として利用されている天然マイカ(雲母)は小さな採掘場の穴から取り出すため、子供が働かされています。
子供たちはわずかの賃金を得るために学校にもいけず、中には崩落で命を落とす子供もいます。
一部の化粧品会社は児童労働を行って採取されたマイカの売買をやめ、マイカ自体を使わない自然に優しい化粧品の開発を行っています。
②弱者支援
障がい者福祉施設などで作られた製品を購入すると障がい者の自立支援になります。障がい者も自分たちが作った製品を購入してもらうことで社会とのつながりも感じることができます。
福岡の障がい者福祉施設では、放置されて問題となっていた竹林の竹を使ってメンマを作るなど、自立支援と自然環境を守る活動を両立させる挑戦も行われています。
③生物多様性
エシカル消費で生物多様性を守ることができます。森林伐採や海洋汚染はあらゆる生き物のすみかを奪います。
エシカル消費では再生紙を使ったり、バナナなど廃棄される植物から繊維をとって利用したりすることで森林伐採を防いでいます。
また、マイボトル、マイストローなどはプラスチックゴミを減らし、自然由来の製品は海洋汚染を防ぐことができます。
こういった積み重ねが地球上の生物の多様性を守り、地球の生態系を守ることにつながります。
まとめ

以上エシカル消費について紹介しました!ポイントは以下の3つです。
エシカル消費は私たちの消費生活にほぼすべてに関わりがあり、例をあげれば枚挙にいとまがありません。だからこそ、エシカル消費は一人ひとりが日常的に実践できることでもあります。
つまり、SDGsに向けて私たち一人ひとりが貢献できるのがこのエシカル消費と言えます。
エシカル消費に絶対的な正解はありません。海外のフェアトレード商品を買うのも、地域の野菜を買うのもそれぞれの課題解決のためのエシカル消費になります。まずは自分のできることから始めてみましょう!




